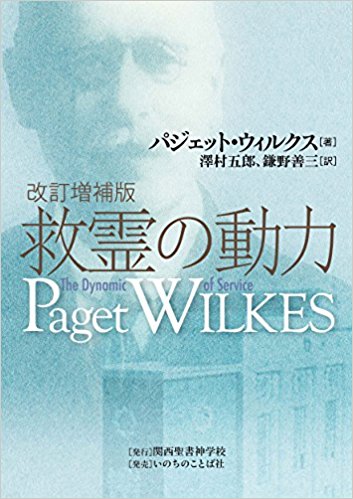[注]この論説は、日本イエス・キリスト教団 信徒局 教会教育室 が発行している『聖書教育教案誌 牧羊者』の「教師養成講座」に、筆者が連載している記事を転載したものです。
第3章 日本伝道のブレイクスルー
第1節 伝道の社会的障壁
ウィルクス師をはじめ多くの伝道者が、伝道のモデルケースとして、主イエスのサマリヤの女への伝道(ヨハネ4章)に注目しています(『救霊の動力』第13章参照)。これを参考にしつつ論考を進めます。
サマリヤの女はイエスに言った、「あなたはユダヤ人でありながら、どうしてサマリヤの女のわたしに、飲ませてくれとおっしゃるのですか」。これは、ユダヤ人はサマリヤ人と交際していなかったからである。(9)
サマリヤは北王国イスラエルの首都でしたが、その都市は紀元前722年にアッシリア帝国の軍隊によって滅ぼされました。イスラエルの指導者ら二万人以上がアッシリアに捕囚として連れ去られ、代わりに帝国の各地から移民がこの地に入植しました。その後、イスラエルの残りの民と入植者の雑婚が進んで、サマリヤ人となったのです。
彼らはゲリジム山に神殿を築いてユダヤ人・エルサレム神殿に対抗しました。そしてモーセ五書を何千個所も改竄(かいざん)して、独自の「聖書」(サマリヤ五書)を作りました。ユダヤ教徒から見れば、サマリヤ教徒は異端です。 前2世紀のマカバイ戦争では、サマリヤ人はセレウコス朝に味方してユダヤ人を攻撃し、ユダヤ人は報復としてゲリジム神殿を焼き討ちにしました。
このような関係ですから、ユダヤ人はユダヤとガリラヤの間を行き来する時、サマリヤを避けてヨルダン渓谷を通りました。 ところがこの時、主イエスはあえてサマリヤを通ってユダヤからガリラヤに帰ることとされました。主がサマリヤ人に伝道することに、重要な意味があったのです。
ただ、聖霊があなたがたにくだる時、あなたがたは力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、さらに地のはてまで、わたしの証人となるであろう。 (使徒行伝1:8)

出典 http://scriptures.lds.org/jpn/biblemaps/11
私たちが日本で伝道するにあたっても、民族や国家、共同体の宗教といった社会的な障壁にぶつかります。これを打ち破るためには、それが何であるか正しく理解して、適切に対処する必要があります。
「日本の宗教人口は2億人」と言われますが、一つの家が神社の氏子であり、寺院の檀家でもあります。この場合、宗教とは地縁と血縁による共同体への所属を意味しています。「キリスト教は、日本を侵略した外国の宗教だ。受け入れたら日本人の民族性が失われる」。そんな意識が染み付いていて、抵抗感のある人が未だに少なくありません。子どもが小学生なら教会学校に通うことを許していても、中学生になったり、「洗礼を受けたい」と言い出したりしたら、教会に行くことを禁じる家庭もあります。
第2節 檀家制度の崩壊
わたしたちの先祖は、この山で礼拝をしたのですが、あなたがたは礼拝すべき場所は、エルサレムにあると言っています。(20)
長寿社会、少子化、地方圏から大都市圏への人口の移動、グローバリゼーションなどによって、日本の家族や地域社会は著しく変化しています。過疎化、限界集落化、地方消滅、認知症社会、無縁社会という現実が広がっており、神社や寺院を支えてきた伝統的な血縁共同体と地縁共同体が瓦解しているのです。
現代の日本人は、7割が無信仰・無宗教を自認するほど、世俗化・宗教離れが進行しています。自分の家がどの宗派のどの寺院の檀家であるのか分からない、あるいは寺院との関係を持たない家庭が増加しています。キリシタン絶滅政策であった檀家制度が崩壊しつつあるのです。
家の宗教・宗派が特に問題となるのは葬式です。
①葬祭の情報サービス会社である鎌倉新書が2014年に関東圏で実施した調査の結果は次のとおりです。
一般葬(参列者が31人以上) 34パーセント
家族葬(参列者が30人以下) 32パーセント
一日葬(一日だけの葬儀) 11パーセント
直葬(葬儀を行わず火葬のみ)22パーセント
②エンディングデータバンクの調査によると、2016年の首都圏での葬式の費用は次のとおりです。
50万円未満 21.1パーセント
100万円未満 26.5パーセント
150万円未満 27.5パーセント
200万円未満 10.2パーセント
250万円未満 6.3パーセント
300万円未満 2.5パーセント
350万円以上 5.7パーセント
③日本消費者協会が実施した第10回葬儀についてのアンケート調査(2014年)によると、葬儀費用の合計は全国平均額で188.9万円でした。これは年々下降しています。その内訳の主なものは次のとおりです。
葬儀一式費用(通夜式・告別式) 122.2万円
寺院への費用(お経、戒名、お布施) 44.6万円
最近の葬式には次のようなトレンドがあります。
①従来一般的であった臨終→密葬→通夜式→本葬儀・告別式→火葬→法要→納骨という流儀が崩れています。
②葬式を一日で済ませるケースが増えています。
③少人数で行う家族葬や直葬が増えています。家族葬に特化した小規模でローコストの葬祭場が増えています。
④僧侶を呼ばずに葬式を行うケースが増えています。
⑤葬儀とは別に「お別れの会」をホテルなどで開催するケースも増加しています。
ちなみに筆者は、タイミングによっては教会の主日礼拝を「追悼礼拝」として、それを本葬儀にしています。また、故人が地域社会で活躍していた場合、ご自宅で「お別れの会」と称して、会葬者100名以上が次々と入退場し献花をする前夜式を行うことがあります。長寿化によって喪主や遺族も高齢者が多くなり、葬式に二日も三日もかけることは体力的に困難になっているからです。
第3節 宗教消滅
この水を飲む者はだれでも、またかわくであろう。しかし、わたしが与える水を飲む者は、いつまでも、かわくことがないばかりか、わたしが与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が、わきあがるであろう。(13〜14)
最近の葬式の変化には、経済的な事情も関係しています。1991年(平成3年)から20年以上続いた平成不況によって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員等の非正規雇用労働者と貧困層が増加し、日本の相対的貧困率は16パーセントに達しています(厚生労働省「国民生活基礎調査」2012年)。生活保護受給世帯数は1990年には62万世帯でしたが、2014年には161万世帯を越えました。
ところが、戒名料の相場はバブル経済の時期にインフレを起こしたまま下がらず、信士・信女が30~50万円、居士・大姉が50~70万円、院信士・院信女が80万円以上、院居士・院大姉が100万円以上だそうです。これでは寺院離れが起こるのも当然でしょう。
そもそもインドの初期仏教や部派仏教は、葬儀と関係が無いものでした。キリスト教など西方の宗教から影響を受けて生まれた大乗仏教が中国に伝わり、そこで儒教の影響を受けて葬式仏教が生まれたようです。戒名は本来、出家者の証であって、在家の信者が持つものではありません。最近は、こういった真実を明示する書籍が次々と発行されています。

- 作者: 村井幸三
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2007/03
- メディア: 新書
- 購入: 9人 クリック: 45回
- この商品を含むブログ (13件) を見る
今や「寺院消滅」の時代と言われています。2015年には約7万7千の寺院がありましたが、そのうち2万以上の寺院が無住(空き寺)であり、約2千の寺院は活動実態がありません。専門家の試算によると、2040年には日本の寺院の3〜4割が消滅しかねない情勢です。ただし宗教学者の島田裕巳氏によると今は、仏教の寺院だけでなく神道の神社も新宗教の施設も含めて「宗教消滅」の時代のようです。
我々キリスト教会の課題は「寺院や神社に代わって、教会が地域の人々の受け皿になれるか」ということです。寺院や神社が日本の地域社会においてソーシャル・キャピタル(社会資本)として果たしてきた公共的な役割は、絶大なものです。「教会は所属する会員=クリスチャンのことしか考えないし、配慮しない」と見られるようでは、教会は地域社会で生き残れないかもしれません。
筆者はこの2年間ほど日本イエス・キリスト教団兵庫教区で婦人部長を務めました。昨年秋の婦人部例会では、水野健牧師を講師にお迎えして「ひと味違う終活セミナー」を開催し、エンディングノートの書き方などを学びました。男性も含めて209名の参加者があり、大変好評でした。この分野は牧会だけでなく伝道においても大きな可能性があります。
クリスチャン企業のライフワークスやブレス・ユア・ホームは、教会に所属していないクリスチャンやノンクリスチャンのための葬儀も行っており、登録した牧師を教会外のキリスト教式葬儀に派遣しています。これは日本宣教において画期的な活動です。
第4節 芋づる式の伝道
あなたは、この井戸を下さったわたしたちの父ヤコブよりも、偉いかたなのですか。ヤコブ自身も飲み、その子らも、その家畜も、この井戸から飲んだのですが。(12)
日本の従来の伝道は「一本釣り」が多かったのですが、終活・葬儀は「芋づる」式の伝道となります。葬儀には故人の子どもや孫、ひ孫まで参列します。
キリスト教式葬儀は自然に伝道となります。葬儀は、誰もが生と死の意味を考えさせられる厳粛な場です。死は、参列する人すべてが、いつかは経験しなければならない現実です。参列者が「私も家族もこうやって葬式をするのだろう」と思えば、その家の宗教はキリスト教に定まります。そこからキリスト信仰に進むのは容易です。
筆者が牧会する神戸大石教会は、宣教開始から86年の歴史があります。筆者は着任してから1年半ほど、ある長老のご自宅に何度も通って教会の歴史を学びました。その長老は教会の歴史と信徒の証しを記録した『群乃足跡』という冊子を何度も発行しました。筆者は長老にお願いして、教会員の家系図を作っていただきました。これらは葬儀だけでなく伝道牧会にも非常に役立ちます。
第5節 文化的障壁のブレイクスルー
あなたがたが、この山でも、またエルサレムでもない所で、父を礼拝する時が来る。(21)
①アレクサンドロス大王の東征(前334〜前323年)以来続くヘレニズム(ギリシア文化のオリエント世界への浸透)の影響を強く受けていました。
②地中海世界を統一したローマ帝国によるパクス・ロマーナ(ローマの平和)のもとで世界中の人と文化に接触していました。
③ユダヤ人やサマリヤ人にも、当時の世界の共通語であるギリシア語を使いこなす人が大勢いました。
これは、我々現代の日本人が経験していることに似ています。
①ザビエルの来日以来ヨーロッパ文化の影響を受けるようになり、さらに江戸幕府末期の開国以来、欧米との交流・貿易が盛んとなりました。
②太平洋戦争の敗戦以降、パクス・アメリカーナのもとで世界中の人と文化に接触するようになりました。特にアメリカニゼーションは著しいものです。
③公教育で世界の共通語である英語を学び、ビジネスなどで使うようになりました。
ただし、主イエスが復活後、世界宣教命令を下したのに、聖霊降臨後も弟子たちは「エルサレム、ユダヤ」から外に出ようとしませんでした。ヘブライスト(アラム語を日常的に使うユダヤ・ガリラヤのユダヤ人)には、サマリヤ人や異邦人に対する拒絶感があったのです。
けれど間もなく、ステパノの殉教に続いて起こった迫害によって散らされた弟子たちによって、サマリヤの伝道が行われ、世界宣教が開始されました(使徒行伝8章)。その弟子たちは長年外国で生活してきたディアスポラ(離散民)であり、ヘレニスト(ギリシア語を日常的に使う人)のユダヤ人でした。
最初期キリスト教は、なぜローマ帝国に広まったのか - カナイノゾム研究室
近年、日本人の受洗者は、国内で洗礼を受ける人よりも、外国で洗礼を受ける人の方が多くなっています。国際化=グローバリゼーションによって、日本人伝道のブレイクスルーが海外ですでに始まっているのです。ただし、ディアスポラ日本人クリスチャンで帰国後に日本の教会につながる人は、2割くらいしかいないようです。
JCFN Japanese Christian Fellowship Network http://jcfn.org/jcfnhome/index.php?lang=ja
最初期の教会では、割礼・食物・安息日・祭儀などの律法の規定と慣習が、異邦人伝道の障害となりました(使徒11:1-3, コロサイ2:16)。今日の日本の教会は、伝道の妨げとなるものに固執していないでしょうか。教会の伝統文化は大切ですが、異なる文化も受容して良いのではないでしょうか。CS教師には、現代の子どもや若者の文化を理解する努力が必要です。
第6節 知的障壁のブレイクスルー
あなたがたは自分の知らないものを拝んでいるが、わたしたちは知っているかたを礼拝している。(22)
第2章で述べたように、日本人には多元的な宗教性があります。また戦後70年間、科学万能主義・唯物論・進化論に基づく無神論的な公教育が為されてきました。このような日本の人々に対して、私たちキリスト者は辛抱強く、聖書・キリスト教が宗教的に唯一の絶対的な真理であることを、証ししなければなりません。そのためにCS教師は、聖書の教理と弁証論を学ぶ必要があります。
教理は日本イエス・キリスト教団が発行している『信仰生活の指針』に簡潔に記されています。1956年に教団から発行された小豆正夫著『キリスト教のおしえ』というカテキズムがありましたが、文体や内容を現代的に修正して、これを用いるのも良いでしょう。弁証論はハロルド・ネットランド、内田和彦 著『キリスト教は信じられるか』(いのちのことば社)をお薦めします。
現代の子どもや若者への伝道においては、メディアが重要な鍵となっています。筆者は聖書・キリスト教関係のマンガを収集して、教会で閲覧・貸出をしています。筆者は2010年にクリスチャンセンター 神戸バイブル・ハウスで、2012年には東京の教文館で、仲間と共に「マンガ・アニメ聖書展」を開催しました。
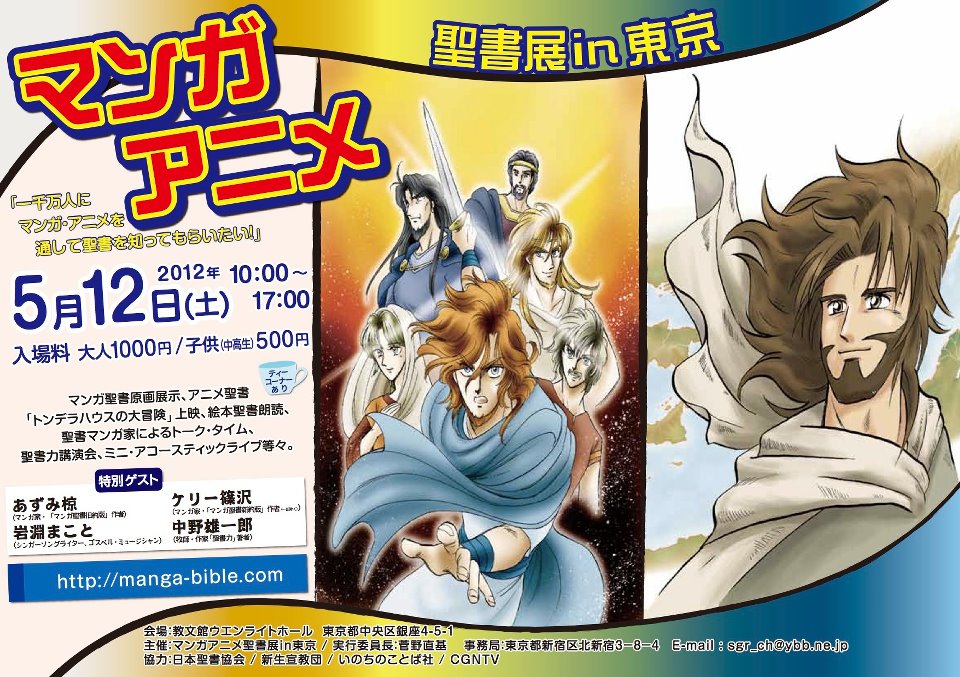
日本人が作るマンガはクオリティーが高くて、世界中で人気があります。ケリー篠沢作『マンガ・メサイア』は700万部以上頒布され、イスラム圏でもキリスト教のリバイバルを起こしています。
「アンダー25」と言われますが、今25歳以下の人たちは、パソコンやインターネットがあって当たり前という環境で育っています。内閣府の調査によると、スマートフォン(スマホ)の所有率は中学生が51.7パーセント、高校生は94.8パーセントにのぼります。スマホによるネットの利用時間は中学生で平均124分、高校生だと平均で170分もあります。
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)とりわけLINE(ライン)が若者たちの交流の場となっています。紙の本を読まず、スマホの画面ばかり見ている若者たちに伝道するためには、YouTube(ユーチューブ)で福音的な動画を公開して、LINEやTwitter(ツイッター)、Facebook(フェイスブック)等で拡散することが有効でしょう。
第7節 霊的障壁のブレイクスルー
神は霊であるから、礼拝をする者も、霊とまこととをもって礼拝すべきである。(24)
あなたと話をしているこのわたしが、それである。(26)
聖書において「霊」という語は、天的な存在の次元を表し、あるいは人が持つ神との交流能力を意味しています。信仰とは、キリストにあって啓示された神との出会いから始まり、神との人格的な交わりを深めていく営みに他なりません。その出会いは、イエスをキリストと信じて新生し、神の御霊を宿している人との交わりを通して、与えられるものです。この交わりは電子空間では足りず、フェイス・トゥ・フェイスが大切ではないでしょうか。
最後に一つの提案をさせていただきます。
①信徒が主体的に、
②自分たちが暮らしている地域で、
③土曜日や祝日に、
④所属している教会を超えて集まり、
⑤子ども伝道あるいは教会学校を行う。
二代目、三代目、四代目と信仰継承が続けば良いのですが、ーー教会から離れた地域に転居したりするうちに、子どもや孫らが日曜朝の教会学校から離れてしまったーーというケースが少なくありません。それならば、自分たちの住んでいる地域で、協力して何とかしようよ、ということです。
探してみたら、案外、近所に同じ教団の信徒や同じ信仰を持つ教派の信徒がいたりします。 今、日本イエス・キリスト教団が推進している「協力教会制度」をこのために活用できないでしょうか。
メンバーが2〜3人でも集まったならば、まずはお互いの課題を分かち合い、テキストブックを読んで学び、共に祈ることから始めてみたら、いかがでしょうか。
もしあなたがたのうちのふたりが、どんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいますわたしの父はそれをかなえて下さるであろう。ふたりまたは三人が、わたしの名によって集まっている所には、わたしもその中にいるのである。(マタイ18:19-20)